「PMOが使えない」と言われる5つの理由!効果的な対策も徹底解説

「PMOなのに使えないと言われてしまった…」
「PMOとして評価されるにはどうすればいいのだろう」
とお悩みではありませんか?
PMOは組織内で重要な役割を担いながらも、その価値が正しく理解されないことがあります。
本記事では、PMOが「使えない」と評価される原因から、その特徴、改善策、そして向いている人・向いていない人の特性まで解説します。
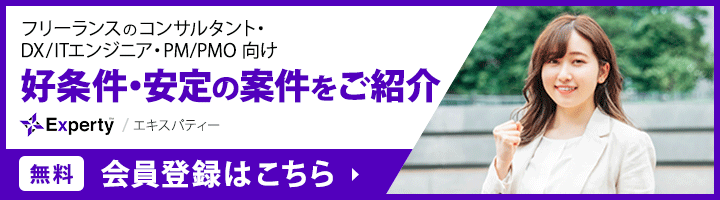
目次
PMOが「使えない」と言われる理由

PMOが「使えない」と評価される原因は、期待と現実のミスマッチにあります。
多くの組織がPMOに過大な期待を抱く一方で、その役割や権限が明確に定義されていないケースが多いのです。
期待とのギャップ
経営層やプロジェクトマネージャーはPMOに対して、プロジェクト全体の問題解決や意思決定の迅速化を期待します。
しかし、実際にはPMOの権限は限定的で、単なる進捗管理や会議運営に留まることが少なくありません。
このギャップが「使えない」という評価につながるのです。
特に大規模プロジェクトでは、PMOに課題解決の即効性を求めるケースが多く見られます。
期待値が高すぎると、どれだけ努力しても「物足りない」と感じられてしまうでしょう。
PMOの役割に対する誤解
多くの組織では、PMOの本来の役割が正しく理解されていない場合があります。
PMOは「万能型の人材」ではなく、プロジェクト全体を支援する「黒子」的存在です。
意思決定はプロジェクトマネージャーや経営層の役割であり、PMOはその判断材料を提供する立場にあります。
この基本的な役割分担の誤解が、PMOへの過度な期待や不満を生み出しています。
また、PMOを単なる「事務局」と位置づける組織も多く、その戦略的な価値が活かされていないケースも散見されます。
関連記事:PMOコンサルタントとは?業務内容や年収、キャリアアップなども解説「使えないPMO」の特徴

「使えないPMO」にはさまざまな共通点があります。
以下で具体的な特徴を解説します。
表面的な課題管理しかできない
PMOとして能力が不足している場合、その人は課題の羅列や記録だけに終始します。
「課題があります」と報告するだけで、解決策の提案や優先順位づけができません。
一方で仕事ができるPMOは、課題の背景や影響範囲を分析し、解決に向けた選択肢を提示できます。
また、数値やデータに基づいた客観的な判断材料を提供することで、プロジェクトの意思決定を加速させる役割を担います。
コミュニケーション能力の不足
PMOの本質はコミュニケーションです。
しかし、スキルが足りないPMOは関係者との対話が一方通行になりがちです。
情報を伝えるだけのケースが多く、相手の反応や本音を引き出せません。
また、経営層とプロジェクトチームの間で言語や視点の翻訳ができず、情報の断絶を生んでしまいます。
反対に効果的に仕事を進められるPMOは、異なる立場の人々の間に立ち、それぞれが理解できる言葉で橋渡しをします。
専門知識やスキルの欠如
プロジェクトの内容に関する基本的な知識がないPMOは、議論の本質を理解できません。
技術的な詳細を完全に把握する必要はありませんが、キーワードや概念の理解は不可欠です。
たとえば、ITプロジェクトのPMOであれば、システム開発の基本的な流れや用語は最低限理解しておくべきでしょう。
また、リスク管理やスケジュール管理などのプロジェクトマネジメントの基礎知識も必須です。
これらの知識がないと、単なる会議の進行役に留まってしまいます。
事務作業に終始している
会議室の予約や議事録作成だけに終始するPMOは、その価値を十分に発揮できていません。
もちろん、これらの事務作業も重要ですが、それだけでは「使えるPMO」とは言えないでしょう。
能力があるPMOは、事務作業の効率化を図りながら、より戦略的な業務にリソースを振り向けます。
たとえば、会議体の整理や重複した報告の一元化など、プロジェクト全体の効率を高める取り組みを主導できるのです。
プロジェクト全体を俯瞰できていない
目の前の作業に埋没し、プロジェクト全体の方向性や目的を見失っているPMOも「使えない」と評価されがちです。
各チームの進捗状況や課題を個別に把握するだけでなく、それらの相互関係や全体への影響を理解する視点が必要です。
また、短期的な問題解決だけでなく、中長期的なプロジェクトの健全性を評価する視点も重要です。
プロジェクトの成功基準を常に意識し、そこからのズレを早期に検知できるPMOが価値を発揮します。
PMOとして「使えない」と言われないための対策

「使えないPMO」のレッテルを貼られないためには、さまざまなアプローチが必要です。
明確な役割を相談する
PMO業務を開始する前に、プロジェクトマネージャーや経営層と期待される役割について徹底的に話し合いましょう。
「何をするのか」だけでなく「何をしないのか」も明確にすることが重要です。
たとえば、意思決定の権限範囲や報告ラインなどを具体的に決めておくと、後々の誤解を防げます。
また、定期的に役割の見直しを行い、プロジェクトのフェーズに合わせて柔軟に調整することも大切です。
この対話を通じて、PMOに対する過度な期待や誤解を事前に解消できます。
PMOの価値を高める情報を収集する
単なるデータ収集ではなく、意思決定に役立つ情報の収集と分析に注力しましょう。
具体的には、各チームの進捗報告から共通の課題パターンを見つけ出したり、過去の類似プロジェクトの教訓を活かしたりする視点が重要です。
また、プロジェクト外部の市場動向や技術トレンドなど、広い視野からの情報も積極的に取り入れるべきでしょう。
これらの情報を整理・分析し、プロジェクトの意思決定者に適切なタイミングで提供することで、PMOとしての存在価値を高められます。
先手を打つ課題管理と解決力を強化する
問題が顕在化してから対応するのではなく、予兆を捉えて先手を打つ姿勢が重要です。
たとえば、進捗の遅れやリソース不足などの兆候を早期に発見し、対策を講じるプロセスを確立しましょう。
さらに、課題を単に記録するだけでなく、解決に向けた選択肢を提示する力も磨いてください。
「この問題に対して、AかBかCの選択肢があり、それぞれにこういうメリット・デメリットがあります」という形で提案できれば、意思決定者の負担を大きく軽減できます。
プロジェクトマネージャーとの協力関係を構築する
PMOはプロジェクトマネージャーの敵ではなく、最大の味方であるべきです。
両者の関係性が悪化すると、プロジェクト全体に悪影響を及ぼします。
そのため、定期的な1on1ミーティングを設け、互いの期待や懸念を率直に話し合う機会を作りましょう。
また、プロジェクトマネージャーの強みと弱みを理解し、弱みを補完する形でサポートすることも効果的です。
信頼関係が構築できれば、プロジェクトマネージャーから「このPMOがいないと困る」と評価されるようになるでしょう。
PMOに向いている人・向いていない人の特徴

PMOは業務内容から向いている人と向いていない人がいます。
ここでは両者の特徴を紹介します。
PMOに向いている人
自己管理能力に優れた人はPMOに適しています。
複数のタスクを同時に進行させながら、締切を守る規律性が求められるからです。
また、「仕組み化思考」を持つ人も向いています。
一度発生した問題を個別に解決するだけでなく、同様の問題が再発しないような仕組みを考える習慣が重要です。
さらに、プロジェクトを「自分事」として捉える当事者意識も不可欠です。
他人事としてただ指示を待つのではなく、主体的に課題を見つけ出し解決に取り組む姿勢がPMOには求められます。
加えて、異なる立場の人々の間に立って調整する「バランス感覚」も重要な資質と言えるでしょう。
PMOに向いていない人
物事を額面通りに受け取りやすい人はPMOに不向きといえます。
プロジェクトでは、表面上の発言と本音が異なることも多く、言葉の裏にある真意を読み取る力が必要だからです。
また、細部にこだわりすぎる完璧主義者も苦労する傾向があります。
PMOは全体最適を考える役割であり、ときには「80点の解決策」を素早く実行することが求められます。
さらに、意見の対立などのコンフリクトを過度に恐れる人も不向きでしょう。
PMOはときに厳しい指摘や調整を行う必要があり、一時的な軋轢を恐れていては職責を果たせないからです。
PMOの案件獲得ならExpertyがおすすめ

PMOとしてのスキルを高単価案件で活かしたいなら、Expertyを活用してみてください。
Expertyは、IT/PMO案件を豊富に取り扱い、案件の多くが月額100万円以上という高単価が特徴です。
また、Expertyの強みは、大手上場企業120社以上との直接契約による質の高い案件と、専任コンサルタントによる手厚いサポートです。
週1時間からフルタイムまで柔軟な働き方に対応しており、利用者のライフスタイルに合わせた案件選びが可能です。
登録者の約90%が継続的に案件を獲得できる実績があり、業界初の給与保証制度も導入されているため安心して働けます。
PMOとしてのキャリアを前進させたいなら、Expertyに登録してみましょう。
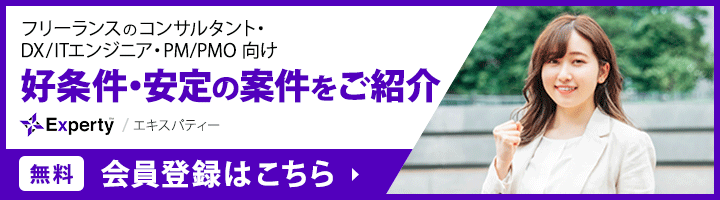
関連記事:PMOフリーランス向けおすすめエージェント5選!選び方やメリットやデメリットを解説
まとめ

PMOが「使えない」と評価される主な理由は、役割の誤解や期待とのギャップです。
価値のあるPMOになるためには、表面的な管理業務から脱却し、プロジェクト全体を俯瞰する視点と先手を打つ課題解決力が不可欠です。
また、PMOに向いている人には自己管理能力や仕組み化思考、当事者意識といった特性があります。
これらの知識を活かしてPMOとしてのキャリアを築きたい方は、Expertyを活用してみましょう。
自分の強みを活かせる案件獲得の可能性が広がります。
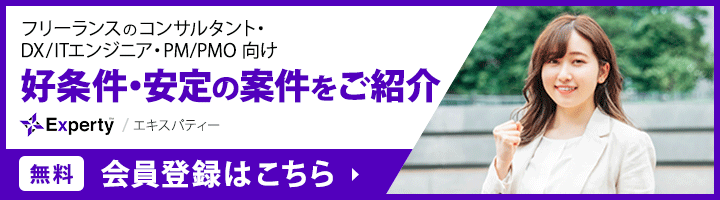
記事監修者の紹介
アメリカの大学を卒業後、株式会社NTTデータに入社。
コンサルティングファームへ転職しデロイトトーマツコンサルティング・楽天での事業開発を経て、取締役COOとして飲食店関連の会社を立ち上げ。
その後、コロニー株式会社を創業。






