業務委託と個人事業主の違いは?注意点も紹介・コロニー株式会社

業務委託や個人事業主という働き方が広まりつつある中、それぞれの違いや注意点を正しく理解しておくことは非常に重要です。
本記事では、これらの概念を明確にし、契約形態や税務処理のポイント、契約時の注意点などを丁寧に解説します。
自営業としての独立を検討している方や、企業から業務委託を受けようとしている方に向けて、実務に役立つ知識を提供します。
目次
業務委託は自営業の扱いになる?

結論から言えば、業務委託で働く個人は広義で自営業の扱いとなります。
業務委託とは、企業と雇用契約を結ばずに仕事を請け負う形態であり、個人の場合は、個人事業主として税務署に登録を行うことが一般的です。
したがって、会社員とは異なり、労働法上の保護を受けず、税務処理も自分で行う必要があります。但し、実態により労働者性が認められると労働基準法等が適用される場合があります。
業務委託とは何か

業務委託とは、企業が特定の業務やプロジェクトを外部の個人や法人に任せる契約形態です。この契約では、指揮命令系統には属しません。受託者は自らの裁量で作業を進め業務を遂行します。
企業が業務委託を利用するメリット
企業側の最大のメリットは、雇用コストの削減と柔軟な人材活用です。
業務委託では社会保険料や福利厚生の負担が不要であり、専門性の高い業務を一時的に外注することが可能です。
また、必要な時期だけ契約できるため、組織の固定費を抑えられます。さらに、特定のスキルを持った人材を迅速に確保できる点も魅力とされています。
個人事業主とは何か
個人事業主とは、法人格を持たずに事業を営む個人のことを指します。
税務署に「開業届」を提出することで、個人事業主として活動が可能です。報酬に応じて「確定申告」を行い、「経費」計上を通じて納税額を調整します。業務委託で受けた案件も、基本的にはこの個人事業として扱われることになります。
関連記事:業務委託はやめた方がいい?メリット・デメリットや向いている職種・フリーランスとの違いを解説
自営業とは何か

自営業とは、自らの責任と裁量で事業を運営し、収益を得る働き方の総称です。
農業、小売業、サービス業など形態は多様で、個人事業主やフリーランスもこれに含まれます。税務上は事業所得を得る者として扱われ、「開業届」や「確定申告」「インボイス制度」への対応など、自らが税務責任を負います。
自営業者は雇用されているわけではないため、労働法に基づく労働時間・有給休暇などの権利は適用されません。加えて、収益の不安定さや経費管理の煩雑さなどもあるため、事業としての計画性が求められます。
業務委託で案件を受けるメリット・デメリット

業務委託として働くことには、自分の裁量で働ける自由度の高さや、収入の上限がないという利点があります。一方で、収入の不安定さや契約条件の不備によるトラブルなど、注意が必要な点も存在します。
ここでは、業務委託で案件を受ける際のメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット
第一に、自分の得意分野やスキルを活かして働ける点が挙げられます。特定の技術や経験がある場合、それを必要とする企業とマッチングしやすく、高単価な案件を得ることが可能です。
第二に、働く時間や場所を自分で選べる自由度が高いことも魅力です。オフィス勤務に縛られず、在宅ワークや地方在住でも仕事を受けられます。
第三に、「経費」として必要経費を申告することで、納税額を適正に調整することもできます。
デメリット
最も大きなデメリットは、収入が安定しない点です。案件が途切れれば収入がゼロになるリスクがあり、常に営業活動やスキル向上が求められます。
さらに、雇用保険や社会保険が適用されないため、自分で国民健康保険や年金、必要に応じ労災の特別加入に加入する必要があります。
次に、業務内容や成果物の定義が曖昧な場合、納品後にトラブルとなる可能性があるため、契約書の作成や確認には細心の注意が必要です。
また、「インボイス制度」導入後は、取引先が課税事業者を求める場合もあり、適格請求書発行事業者として登録すべきか判断が必要です。
業務委託で結ぶ契約の種類

業務委託契約には大きく分けて「請負契約」と「(準)委任契約」の2種類が存在します。それぞれ契約の性質や責任の範囲が異なるため、契約前に十分な理解が必要です。
①請負契約
請負契約は、完成した成果物に対して報酬が支払われる契約形態です。
たとえば、Webサイトの制作やアプリの開発など、明確な納品物がある場合に用いられます。この契約では、成果物の完成が報酬の支払い条件であるため、受託者には成果責任が課されます。完成品が契約内容を満たさない場合、修正や再提出を求められることになります。
また、発注者は作業過程に介入する指揮命令はできません。但し、仕様・検収・進捗確認等は契約上の必要な管理として実施できます。
仕事を請け負う際の前提条件として、納期や成果物の仕様などを契約時に明確に取り決めておく必要があります。これらを契約時に明確にすることでトラブルを回避できます。
②(準)委任契約
準委任契約は、一定の作業や業務の遂行を目的とする契約です。成果物の完成ではなく、業務そのものを遂行することに対して報酬が発生します。
たとえば、コンサルティングやエンジニアの技術支援、事務作業の一部代行などが該当します。責任は「結果」ではなく「過程」にあるため、完成義務は発生しませんが、善管注意義務(善良な管理者の注意)を持って業務にあたることが求められます。
業務を開始する前の準備

開業届の提出
「開業届」を税務署に提出します。「開業届」の提出は税法上の義務であり、登録をしておくことで、税や補助金・助成金の申請などのメリットを受けられます。
国税庁では、青色申告など後続手続きのため早めの提出を推奨しています。
インボイス制度の登録
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、登録事業者は、適格請求書の発行が可能です。
登録は任意ですが、取引によっては、適格請求書の発行が求められる場合も増えています。必要に応じて、登録の準備をすすめましょう。
業務委託の偽装請負とは

偽装請負とは、業務委託契約の形式をとりながら、実態としては企業の指揮命令下で働かせることを指します。
これは労働者派遣法や労働基準法に違反する可能性があり、企業側・受託者側の双方にとって重大なリスクを伴います。
具体的には、業務委託契約にもかかわらず、業務の進行に対して発注者が細かく指示を出したり、勤務時間や場所を一方的に指定したりするケースが該当します。これにより、受託者は労働者とみなされ、雇用関係が認定される場合があります。
厚生労働省のガイドラインでは、業務の遂行に関して「独立性」が確保されていない場合、委託契約ではないと判断される可能性があるとされています。
企業は、業務範囲や成果物を明確にし、指揮命令系統を介さない体制づくりが求められます。受託者としても、指示内容に違和感を感じた場合は、契約内容の見直しや法的助言を受けることが重要です。
業務委託契約書の作り方

業務委託契約書は、契約内容や責任範囲を明文化し、トラブルを防止するために欠かせない書類です。請負契約か委任契約かを明記し、業務内容、納期、報酬、秘密保持など、具体的な条件を詳細に盛り込む必要があります。
また、2024年11月1日施行のフリーランス法により、発注者には取引条件の書面明示、支払期日・ハラスメント相談体制等の義務が課されています。これらの要件を満たしているか確認が必要です。
契約書の作成は、法的知識を要するため、雛形の流用ではなく、自社または個人の業務内容に合わせたカスタマイズが重要です。可能であれば弁護士や専門家によるレビューを受けておくと安心です。
チェックするべきポイント
1. 【契約の類型と目的】請負契約か委任契約かを明記し、その目的や成果物を明確に定義しておくこと。
2. 【業務の範囲】どこまでが受託者の責任範囲かを具体的に示し、業務過多やトラブルを防止する。
3. 【報酬・支払条件】金額、支払期日、遅延時の対応、源泉徴収の有無などを記載。
4. 【納期・スケジュール】納品物の提出期限や中間報告の有無、期日変更時の調整方法を明記。
5. 【成果物の所有権】納品後の知的財産権の帰属先を明示し、トラブルを未然に防ぐ。
6. 【秘密保持】業務で知り得た情報を第三者に漏洩しない旨の条項を盛り込む。
7. 【契約期間と解除条件】契約の開始日と終了日、中途解約の可否、違約金の有無などを設定。
8. 【損害賠償】成果物の瑕疵や納期遅延時にどのような責任が発生するかの規定を設ける。
9. 【インボイス制度への対応】適格請求書の要否や登録番号の記載有無を契約文書で合意しておく。
10. 【紛争時の対応】管轄裁判所や仲裁機関をあらかじめ取り決めておく。
2者間契約・3者間契約とは

2者間契約とは、発注者と受託者の間で直接締結される契約を指します。一方、3者間契約とは、発注者・仲介事業者・受託者の三者が関与し、それぞれに契約関係が発生する形態です。案件の規模や管理体制に応じて、どちらの形式を選ぶかが変わります。
3者間契約を結ぶメリット・デメリット
メリット:
* 受託者は営業活動を行わずとも案件獲得が可能。
* 発注者側は仲介事業者によるスクリーニングを経た人材を活用できる。
* 報酬や納期の調整が仲介事業者を通じてスムーズになる。
デメリット:
* 仲介手数料が発生し、報酬額が減少する傾向がある。
* コミュニケーションが三者間で煩雑になるケースも。
### 2者間契約を結ぶメリット・デメリット
メリット:
* 直接契約するため報酬額が高くなる傾向がある。
* 契約条件や成果物について、当事者間で柔軟に調整が可能。
* コミュニケーションがシンプルで、業務遂行が効率的になる。
デメリット:
* 案件獲得には自身で営業活動を行う必要がある。
* 報酬未払いなどのリスクに対する保険が薄くなる。
関連記事:PMOは業務委託で稼げる?年収やフリーランスのメリット・デメリット – コロニー株式会社
案件を探すならExperty
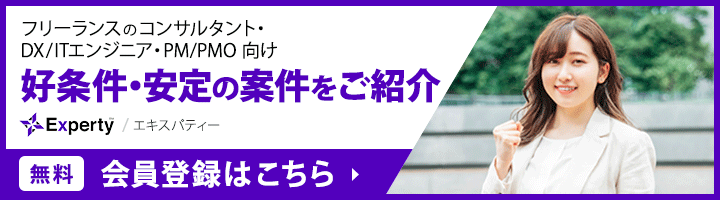
業務委託の案件探しにおいて、信頼できるプラットフォーム選びは非常に重要です。Expertyは、IT・クリエイティブ業界を中心とした高単価案件を数多く掲載しており、スキルに応じたマッチングが可能です。
契約形態や働き方も多様で、初めて業務委託を経験する方でも安心して始められるサポート体制が整っています。
報酬の支払いサイトや契約形態の明示、インボイス制度への対応実績もあるため、制度面の不安がある方にもおすすめです。
[Expertyへのお問い合わせはこちら](https://qolony.co.jp/experty/freelance/top)
まとめ
業務委託と個人事業主は混同されがちですが、法的・契約的には明確な違いがあります。どちらの立場にあるかを正しく理解することで、リスクの回避や契約の適正化が図れます。インボイス制度や確定申告、経費処理などの制度対応も含め、専門的な知識が求められる場面が増えています。
安易に「業務委託=自由な働き方」と捉えるのではなく、自営業者としての責任と権利を理解したうえで、自分に適した働き方を選ぶことが大切です。安心して働くためにも、契約書の確認や適正な手続きを怠らないよう心掛けましょう。
記事監修者の紹介
アメリカの大学を卒業後、株式会社NTTデータに入社。
コンサルティングファームへ転職しデロイトトーマツコンサルティング・楽天での事業開発を経て、取締役COOとして飲食店関連の会社を立ち上げ。
その後、コロニー株式会社を創業。






