シンクタンクとは?コンサルとの違いや意味、年収・仕事内容まで解説・コロニー株式会社

シンクタンクとは、政治・経済・社会課題などを調査・分析し、政府や企業に向けて提言やレポートを提供する「研究機関・知的サービス組織」です。
近年は政策提言にとどまらず、DXや業務改革などの実行支援まで担うケースも増え、戦略コンサル志望者にとって有力なキャリアの選択肢になっています。
本記事では、コンサルとの違い、仕事内容、年収相場、向いている人や必要スキルまでを整理します。
目次
そもそもシンクタンクとは?

シンクタンクは政府や民間企業などに対して、政治的・社会的・経済的問題に焦点を当て情報を分析し、その分野の専門知識や研究結果に基づいた提言を行う研究機関です。
国際政策・経済政策・環境問題・教育政策・地域開発など、幅広い分野で活動しています。
さらに近年は、調査結果を「提言」で終わらせず、政策の実装支援や企業の変革支援まで求められるようになりました。
背景には、社会課題の複雑化と、意思決定に求められるエビデンスの高度化があります。
例えば脱炭素や人口減少は、制度設計だけでなく産業構造や地域経済、企業の投資判断まで絡み合うため、定量データと現場の知見を統合した分析が欠かせません。
こうした領域では、学術的な手法で論点を構造化し、統計・経済モデル・国際比較などを用いて論拠を示せる組織が重宝されています。
シンクタンクの起源と歴史
シンクタンクの源流は19世紀後半のイギリスに見られ、社会改良を掲げるフェビアン協会のように、政策思想を形にして提言する組織が登場しました。
20世紀初頭のアメリカではブルッキングス研究所が設立され、政府運営や経済政策を研究し、公共政策の意思決定を支える役割を担いました。
日本では高度経済成長期に、経済計画や産業政策、社会インフラ整備の需要が高まり、官民双方の「調査・分析」の受け皿としてシンクタンクが拡大しました。
近年は受託調査に加え、営利性の高いコンサルティングへ重心を移し、企業変革の伴走まで担う組織が増えています。
シンクタンクの種類
シンクタンクは大きく「政府系シンクタンク」と「民間系シンクタンク」に分けられます。
政府系シンクタンクは、経済分析や政策の立案・提言などを行う政策研究機関としての性格が強く、公共性を重視する非営利的な位置付けになりやすいでしょう。
一方で民間系シンクタンクは、企業の戦略立案や戦略実行支援などを行い、収益事業としてコンサルティングを展開する営利的な側面を持ちます。
民間系がコンサルティングを強化した背景には、企業側の課題が「調査レポートの入手」だけでは解決しなくなった事情があります。
例えば、事業ポートフォリオの再設計やDX推進は、分析だけでなく業務設計・システム実装・組織変革まで連動します。
そのため、調査と実行を一体で提供できる体制が競争力となりました。
なお民間系はさらに、金融機関系、事業会社系、独立系などに細分化できます。
金融機関系は市場・金融に強く、グループのネットワークと情報力を活かしやすい一方、事業会社系はITや製造、エネルギーなど親会社の事業領域に根差した専門性を築きやすい傾向があります。
シンクタンクの企業一覧
以下で、シンクタンクの企業例を確認していきましょう。
政府系シンクタンク
政府系シンクタンクの企業例として、経済社会総合研究所、経済産業研究所(RIETI)、日本国際問題研究所(JIIA)、防衛研究所、産業技術総合研究所などが挙げられます。
経済社会総合研究所は国の経済統計やGDP関連の分析を通じて政策判断の基盤を提供し、RIETIは産業政策の理論面を支える研究・提言に強みがあります。
JIIAは外交・安全保障の調査研究を担い、防衛研究所は国防・軍事史を含む安全保障研究の専門機関です。
産業技術総合研究所は産業技術の研究開発(R&D)を推進し、技術面から産業競争力を支える役割を果たします。
民間シンクタンク
民間シンクタンクの企業例は野村総合研究所、日本総合研究所、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、大和総研、三菱総合研究所、NTTデータ経営研究所、富士通(旧富士通総研)、日立総合計画研究所などです。
民間シンクタンクは大きく金融系シンクタンクと事業系シンクタンクに分けられます。
金融系は、野村・三菱UFJ・SMBC・大和など、親会社の金融グループと密接に連携し、金融市場や規制、産業動向の情報力を強みにします。
グループ内の受託案件が一定比率を占めるため安定性がある一方、外部企業向けのコンサル案件を拡大し、収益源を多角化する動きも見られます。
事業系は、三菱総研やNTTデータ、富士通、日立などのように、親会社の事業領域(IT、製造、エネルギー等)に基づく知見を活かし、技術・業務の実装力を強めやすい点が特徴です。
親会社からの受託で磨いた実行力を、外部企業の改革支援へ横展開するモデルです。
シンクタンク系コンサルティングファームとは?
シンクタンク系コンサルティングファームはどのような企業なのでしょうか。
シンクタンク系コンサルティングファームとは、政府や地方自治体などの依頼を受けて、調査やコンサルティングを行うファームのことです。
一般的なコンサルティングファームと比較すると、高い調査力を特徴としており、特に金融業界に関するコンサルティングに強みがあります。
加えて、親会社に大手金融機関や企業グループを持つケースが多く、情報基盤や人材育成、案件の安定性で優位に立ちやすい点も見逃せません。
代表例として野村総合研究所(NRI)や三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)などが挙げられ、官公庁案件の調査・提言と、民間企業の戦略・実行支援の両方を担う「官民二正面」の立ち位置が特徴となります。
関連記事:コンサルタントの年収を徹底解説!報酬が高い理由や年収アップの方法も紹介
シンクタンクの主な業務内容
シンクタンクの業務は、調査・研究業務、経営戦略領域、業務・システム領域の三つに分けて捉えると理解しやすいでしょう。
調査・研究業務では、中央省庁や自治体向けに政策提言のための委託調査を行い、経済指標の分析や制度設計の論点整理、報告書の取りまとめを担います。
経営戦略領域では、民間企業向けに中期経営計画の策定、事業ポートフォリオの再設計、M&Aの検討支援など、経営層の意思決定に直結するテーマを扱います。
業務・システム領域では、IT戦略の策定や大規模システム開発のPMO支援、データ基盤整備など、実行フェーズに踏み込む支援が中心です。
近年はDX推進やサステナビリティ(ESG)対応が増え、調査と実装が一体化した案件が拡大しています。
コンサルタントとシンクタンクの違い

コンサルタントとシンクタンクの違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | コンサルタント | シンクタンク |
|---|---|---|
| 業務内容・役割 | 課題設定から解決策の設計、実行支援までを短期集中で推進 | 調査・分析を通じて提言を作成し、必要に応じて実装支援も行う |
| クライアントの担当部門 / 主要クライアント | 企業の代表取締役や役員など経営層(CEO/CXO)、全社横断の改革部門 | 官公庁・自治体、企業の事業部門や専門部署(部長・リーダークラス) |
| コンサルテーマの特徴 | 課題設定から入ることが多く、論点整理・打ち手設計まで求められやすい | 調査テーマが具体的に定義されていることが多い |
| 求められるスキル | 仮説構築、プレゼン、ファシリテーション、高いコミュニケーション力、合意形成力 | 専門知識、リサーチ力、分析力、統計・データ分析、論理的執筆 |
| ビジネスモデル | コンサルタント自身の能力(問題解決力・推進力)が商材 | 情報・調査データ・分析結果(レポート)が商材 |
| 採用・評価制度 | 論理的思考力や提案力、対人スキルが評価されやすい | 研究・レポート作成経験、専門性が評価されやすい |
| キャリアパス | 経営プロフェッショナルとして事業会社幹部や起業などへ広がりやすい | 特定領域のスペシャリストとして専門性を深化させやすい |
クライアントの担当部門
コンサルタントのカウンターパートは、企業の代表取締役や役員が多くなる傾向があります。
コンサルタントは主に企業の経営課題を解決し、クライアントのビジネス目標や利益に焦点を当てています。
そのため、情報収集や戦略の提案・実行時に、経営層と密に関わることが必然的に多くなります。
一方でシンクタンクは、特定分野で活躍している部長やリーダークラスがカウンターパートになるケースが多くなります。
シンクタンクは研究や分析に特化した組織なので、あらかじめ依頼テーマが明確化されており、その分野に詳しいリーダークラスの方が依頼者となります。
業務内容の違い
コンサルタントの場合、「組織・業務体制の改革」「M&A戦略」など、依頼されるテーマが課題設定からであるケースが多いです。
そのため、情報収集をしつつ、クライアントと相談しながら戦略の策定・実行を行います。
加えて近年は、新規事業立案や業務改革(DX)など、実行フェーズに踏み込むプロジェクトが増え、短期間で意思決定と合意形成を回しながら成果を出す設計が求められます。
一方でシンクタンクは、依頼時に調査テーマや分野がすでに明確化されているため、業務の大半が研究や分析に費やされます。
例えば官公庁委託での経済指標分析や制度評価の調査設計、産業別の将来シナリオ作成などが典型です。
加えて近年は、調査・研究に加えて、特定専門領域の導入支援や政策実装支援など「コンサルティング」色の強い業務も増え、提言から実装へつなぐ役割が拡張しています。
求められるスキルの違い
コンサルタントは、クライアントと協力しながら企業の課題解決に取り組みます。
戦略の策定・提案時には筋道を立てた提案を行い、クライアントに納得してもらうことが重要です。
答えのない課題に対して論点を切り出し、検証可能な仮説に落とす「仮説構築力」や、会議体を設計して合意形成を前進させるファシリテーションが成果を左右します。
シンクタンクでは特定分野での研究や調査を依頼されることから、専門知識やリサーチ力が求められます。
加えて、統計・公開データ・学術知見を扱い、再現性のある根拠を示すデータ分析能力、読み手の政策判断や投資判断に耐える論理的執筆力が重要です。
両者を比べると、コンサルはスピード感を優先しやすい一方、シンクタンクは網羅性と精緻さを優先する場面が多いでしょう。
ビジネスモデル
コンサルタントの売りは「コンサルタント自身の能力」です。
クライアントの課題解決に必要なコンサルタントの確保や、プロジェクト期間によって報酬やコストは変動します。
これを踏まえた上で自身のスキルを活用してクライアント企業の課題解決に取り組むため、クライアントが望む結果を導き出せなければ評判を損ね、コンサルタント自身の利益も損ねてしまいます。
一方でシンクタンクは、すでに定義されたテーマについて高度な分析・研究を行い、まとめることが主な仕事なため、提供する「情報」(成果物)がシンクタンクの商材と言えるでしょう。
シンクタンクでは案件1つに対して報酬が設定されるプロジェクト報酬型が多く、報酬制度もコンサルタントとの大きな違いのひとつです。
採用・評価制度
コンサルタントにおいては、高いコミュニケーション能力や論理的思考力、クライアントに納得してもらえる提案力を兼ね備えた人材が評価されやすいです。
コンサルティング業界が初めての方でも実績や経験が豊富であれば、コンサルタントとして採用されやすく、活躍の場も広がります。実力主義な業界なので、積極性を持つことも重要です。
一方シンクタンクは、学術的な研究やレポート作成の経験がある人材が評価・採用されやすい傾向にあります。
大学や大学院の新卒採用に積極的で、勤続年数も長い人が多いです。そのため、年功序列の色が強いのもシンクタンクの特徴と言えます。
コンサルティングファームとシンクタンクの年収相場

コンサルティングファームとシンクタンクは報酬制度も異なることから「年収にも差が出るのでは?」と考える人も多いです。
そこで本章では、両者の年収相場についてコンサルティングファームとシンクタンクに分けて解説します。
どちらもスキルや経験次第で年収が上がりやすい仕事です。「自分の能力を発揮しやすい分野はどちらなのか?」適性や得意スキルと照らし合わせながら、参考にしてみてください。
コンサルティングファームの年収相場
コンサルティングファームに在籍しているコンサルタントの年収は推定400〜1,200万円で、スキルや役職によって変動します。
役職や経験ごとの推定平均年収は以下の通りです。
| 役職 | 年齢 | 経験年数 | 年収相場 | 業績賞与 |
|---|---|---|---|---|
| アナリスト | 22〜28歳 | 0〜3年 | 400〜800万円 | 固定給の20% |
| コンサルタント | 25〜35歳 | 0〜6年 | 900〜1,300万円 | 固定給の20% |
| マネージャー | 28〜40歳 | 2〜10年 | 1,400〜2,000万円 | 固定給の30% |
| プリンシパル | 32〜45歳 | 5〜15年 | 1,700〜2,500万円 | 固定給の30% |
| パートナー | 35歳以上 | 7年以上 | 2,500万円以上 | 業績次第 |
アナリスト・コンサルタントクラス
若手層(22〜28歳、経験0〜3年)の年収は概ね推定400〜800万円が目安となります。
プロジェクト単位の評価が賞与に反映されることが多く、成果の出し方や上司評価によってボーナスがブレる点も特徴です。
マネージャー・シニアマネージャークラス
中堅層(28〜40歳、経験2〜10年)では推定1,400〜2,000万円以上がレンジに入ります。
個人の分析力に加えてチーム運営や品質管理、納品責任が増え、売上や稼働を管理するほど報酬が上がりやすくなります。
パートナー・ディレクタークラス
上級職(35歳以上、経験7年以上)では推定2,500万円以上まで広がります。
案件獲得(受注額)に応じた成果報酬の比重が高まり、営業力とブランド構築が年収を大きく左右します。
フリーランスコンサルタントは年収が高い?
フリーランスコンサルタントの年収は、ファーム在籍者の2〜3倍になることもあり、大幅に年収が上がることは珍しくありません。
ただし、コンサルティングを行う業界や分野によって年収は変動します。
フリーランスでは1〜3ヶ月程度で契約を更新するケースが多く、パフォーマンス次第では単価が上がりやすい特徴があります。
年収が高くなりやすい理由は、仲介マージンが小さい、または直接契約で手取りが増える点にあります。
例えば月単価150〜250万円で稼働できれば年収は1,800〜3,000万円の水準が視野に入ります。
一方で案件途絶のリスクや福利厚生の欠如はデメリットで、稼働率が落ちた月は収入が大きく下がる可能性もあります。
複数案件を並行しつつ次の案件獲得に向けた営業活動も必要になるため、エージェントを活用する人が多いのはこのためです。
関連記事:コンサルタントの仕事内容とは?年収ややめとけと言われる理由を解説 – コロニー株式会社
Expertyでは大手上場企業120社以上とのプロジェクト案件を紹介しています。
コンサルタント未経験の方でも、担当者がコンサルティングの基礎やプロジェクト進め方をレクチャーするため、自分の得意分野で活躍することが可能です。
新規事業・IT/PMO・人事・マーケティング・エンジニアなど幅広い分野の高額案件を紹介しているので、独立を考えている方は活用してみてください。
Expertyへの登録はこちら
日本の5大シンクタンクは?

日本の主要5社として、野村総合研究所、三菱総合研究所、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、日本総合研究所、みずほリサーチ&テクノロジーズが挙げられます。
野村総研はITの実行力とコンサルを一体で提供できる点が強みで、三菱総研は官公庁案件や科学技術・社会システム領域の知見が厚い傾向があります。
MURCは三菱UFJグループのネットワークを背景に金融・産業政策に強く、日本総研はSMBCグループの基盤を活かしつつ経済調査からITまで幅広い領域を担います。
みずほリサーチ&テクノロジーズは金融・産業調査に加えて技術・ITの機能も抱え、官民双方での課題解決に関与しています。
### シンクタンクの年収相場【主要5社を比較】
シンクタンクの年収相場は350〜1,500万円で、経験値やスキルによって2,000万円以上稼ぐ人もいます。
なお、5大シンクタンクの推定平均年収は以下の通りです。
| 企業名 | 平均年収(目安) |
|---|---|
| 野村総合研究所 | 900万円台後半〜1,000万円前後 |
| 三菱総合研究所 | 800万円台後半〜900万円前後 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 800万円台後半〜900万円前後 |
| 日本総合研究所 | 700万円台〜800万円前後 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ | 700万円台後半〜900万円 |
アカデミック要素の強い分野だからこそ高度な専門知識や豊富な経験が求められるため、年収も高額になりやすい傾向があります。
実際の年収は職種(研究・政策、戦略、IT/PMO)や役職、勤務地、賞与比率によって変動するため、応募時は求人票や面談で内訳まで確認すると安心です。
役職別の年収相場
シンクタンクでは研究員・アソシエイトから始まり、主任研究員、上席研究員、シニアマネージャーといった役職へ進むのが一般的です。
コンサルファームに比べると年功序列的な側面が残る企業もあり、上がり方は緩やかでも安定しやすい一方、成果連動のインセンティブは相対的に小さくなりやすいでしょう。
以下は目安の年収モデルです。
研究員・アソシエイトクラス
若手層(新卒〜3年目程度)は年収400〜600万円程度が目安となります。
リサーチ、データ収集、資料作成など基礎業務が中心で、統計や情報ソースの扱い方、論理構成を磨く期間になります。
主任研究員・マネージャークラス
中堅層(経験4〜10年程度)は年収800〜1,200万円程度がレンジに入りやすいでしょう。
専門性を深めつつ、プロジェクト管理や品質担保、部下育成などの役割が増え、案件をリードできる力が評価されます。
上席研究員・シニアマネージャークラス
上級職(経験10年以上)では年収1,300〜1,800万円以上が視野に入ります。
官公庁や大企業とのネットワーク構築、提案活動、部門運営などの比重が上がり、組織として成果を出す力が求められます。
なぜ年収に差が生まれるのか?ビジネスモデルの違いから解説
コンサルは高単価・短期集中のプロジェクトが多く、成果に応じたインセンティブが厚くなる傾向があります。
特に上位職になるほど受注額や売上責任が評価に直結し、年収の伸びが大きくなります。
一方シンクタンクは、安定的な受託や中長期プロジェクトが多く、賞与比率が高い企業もあります。
さらに民間シンクタンクでは親会社(銀行・商社・大企業グループ)の給与水準や制度が影響することがあり、同じ職位でも企業によって水準差が生まれやすい構造となります。
コンサルタントとシンクタンクはどんな人が向いている?必要なスキルは?

コンサルタントとシンクタンクはビジネスモデルの違いから、求められるスキルにそれぞれ特徴があります。
そこで本章ではコンサルタントとシンクタンクの二つに分けて解説します。
コンサルタントに向いている人・必要なスキル
コンサルタントはクライアント企業の課題解決をサポートする仕事です。
そのため「クライアントファーストで動ける」人は評価も得られやすく、活躍の場も自然と広がります。
また、情報収集を行い得た情報を基に戦略や改善策を策定・提案する論理的思考力が求められます。
ここで重要なのは、情報を集めるだけでなく仮説を構造化し、検証の順序を設計できることです。
さらに、経営層から現場従業員までヒアリングを行うため、ステークホルダーの利害を調整し合意形成を前進させる対話力が欠かせません。
加えて近年は、IT、製造、金融など特定業界の深いドメイン知識・経験が、提案の説得力と実行可能性を左右します。
幅広い領域を扱うからこそ、常に学び続ける姿勢が強みとして効いてくるでしょう。
シンクタンクに向いている人・必要なスキル
シンクタンクはアカデミック要素の強い報告書を作成することから、その分野における高い専門知識を持った人が活躍しやすい傾向にあります。
さらに中・長期で取り組むことを前提とする案件も多く、ひとつの分野を継続的に研究できる人も向いているでしょう。
また、膨大な情報を元に分析や調査を行い、導き出した研究結果をわかりやすく論理的にまとめる力も必要です。
加えて近年は、官民双方の関係者と連携して政策や施策を前に進める場面が増え、調整型のコミュニケーション能力も重要になっています。
専門分野も、政策立案(パブリックアフェアーズ)、環境・エネルギー、金融、IT/DXなど多岐にわたり、データ分析と実務知見を橋渡しできる人材は特に重宝されるでしょう。
キャリアパスの違い|専門性の深化 vs 経営への道
シンクタンクは特定領域の第一人者(有識者)として専門性を深めるキャリアパスを描きやすく、政策領域・産業領域での評価が積み上がるほど存在感が増します。
一方コンサルは、経営層の意思決定に近い場所で総合的に課題を扱う経験が蓄積し、CXO、起業、事業会社幹部など「経営への道」に展開しやすい傾向があります。
転職市場では、コンサル経験は汎用性として評価されやすく、シンクタンク経験は専門性として評価されやすいという違いも押さえておくとよいでしょう。
シンクタンクから独立して、コンサルタントとして案件獲得するならExperty
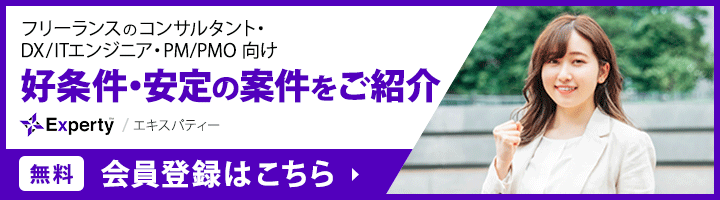
シンクタンクからコンサルタントとして活動する場合、エージェントを活用することで、条件の良い案件を獲得しやすくなります。
Expertyでは、大手上場企業120社を超えるコンサルティング案件の紹介を行っており、半数以上が100万/月以上の案件です。
さらに業界初の給与保証によって、登録者の90%以上が安定して案件を継続しています。
コンサルタント未経験者でも、担当者がコンサルの基礎やプロジェクトの進め方をレクチャーするため、安心して案件を進めることができます。
自分の得意分野でキャリアアップを目指す方は、ぜひ活用してみてください。
Expertyへのお問い合わせはこちら
まとめ
コンサルタントとシンクタンクは、いずれも「クライアントの支援」を担うため混同されがちです。しかし実際には、ビジネスモデルも役割も異なります。だからこそ、両者の違いを理解しておくことは重要です。
自分の得意分野や適性に合った働き方を選べれば、キャリアの選択肢は広がります。幅広い領域で企業の経営戦略に関する課題を扱い、実行まで伴走したい場合はコンサルタントが向いているでしょう。
一方で、特定分野の専門知識を深め、政策・教育・環境などの社会課題の解決を支えたい場合は、シンクタンクが適しています。
転職を考えている方は、本記事の内容を参考に、今後のキャリア設計の幅を広げてみてください。
また、働き方の選択肢としてフリーランスという道もあります。
フリーランスは会社員の給与収入に比べて、スキルや経験が報酬に反映されやすく、高報酬を目指しやすい点が魅力です。
Expertyでは、高単価の案件を多数取り揃えております。興味のある方は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。
Expertyへのお問い合わせはこちら
記事監修者の紹介
アメリカの大学を卒業後、株式会社NTTデータに入社。
コンサルティングファームへ転職しデロイトトーマツコンサルティング・楽天での事業開発を経て、取締役COOとして飲食店関連の会社を立ち上げ。
その後、コロニー株式会社を創業。






